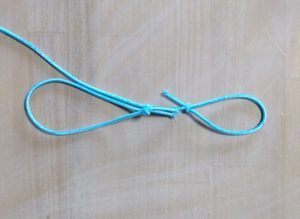ただ今、陶芸体験割引き中!
大人1名 3000円
小人1名 2500円
● 湯呑み、茶碗、抹茶茶碗、
多肉植物や観葉植物の植木鉢、
酒器やシガーの灰皿なんかも作れます。
あんまり難しいのは陶芸体験じゃあ無理かな。
その場合はメンバーになってください(笑
さあ、今こそ陶芸体験してみよう!
************
陶芸体験でもいろいろある
一言で陶芸体験と言ってもいろいろあるんです。
手びねりで手回しロクロを使って作ったり、たたら作りでお皿をつくったりいろいろあります。
ウチでは、陶芸体験で電動ロクロを使ってもらいます。
いきなりの初心者が電動ロクロを回せるのかといった疑問もあるかと思いますが、結構できちゃうんですね。
うちでの陶芸体験のほとんどの方が、自称初めてさん?なんですが、皆さん無難に回しています。
きちんとロクロの使い方と手順を教われば、それこそ幼稚園児からお年寄りまで、老若男女、全ての人が電動ロクロで作品を作れます。
ロクロのひき方もコツがあるんですね。
特に、初心者の方がある程度ひけるように、作陶のコツを教われば、そんなに難しいものでもありません。
まあ、プロのような作品が作れるかといったら、そこは難しいですが、初心者の方なりにちょっと使える湯のみや茶碗は普通に作れるようになります。
以下、手順を書いていきましょう。
陶芸体験をロクロでやる際の簡単な手順
以下、陶芸体験のロクロでの手順ですが、かなりシンプルに記入しています。
そこの所はご了承ください。
・土練りをやる場合は、土練りの仕方を教わります。
これは力作業ですので、これを飛ばす所も多いです。
・続いて、簡単に電動ロクロの動かし方を教わります。
・土ころしで土を上げ下げします。
・湯のみをひいていきます。
・その後は数点の作品を作っていきます。
このあたりがおおまかな陶芸体験での手順になります。
ちなみに、作品の高台削りや釉掛けなどはやりません。
と言うより、1日でこれら全ての作業は無理なんですね。
陶芸体験での作品を作った後は
陶芸体験などで作品を作った後、それらはどうのようにして完成するのか見てみましょう。
・まずロクロでひいた作品を一日置いてちょいと乾燥させてから高台を削る。
・削って成型が完成したものをムロ(作品棚)で乾かす。
これが1週間から2週間かけて乾燥させます。
・その後に窯で素焼きをする。
・素焼きした後で、釉薬を掛ける。
・その後、本焼きで焼き上げる。
どうでしょう。結構、工程がたくさんありますね。
これらの作業を陶芸体験の一日でやるのは到底無理なんです。
なので、陶芸体験というのはたいてい、手びねりやロクロで作品を作るまで。
ここまでで終了します。
残りの高台削りや釉掛けは教室の方でやって、焼き上げた作品をお送りする形になります。
あるいは近隣の方は直接取りに来てもらうとか。
こうして完成した作品に出会えるのが、また楽しみになるんですよね。

陶芸体験の作品を還元焼成で焼く
ウチでは陶芸体験の作品も全て還元焼成で焼いています。
還元焼成とは焼成時の酸素を制限して焼く技法で、焼き上がった作品は高級感のある渋めの作風に仕上がります。
反対に酸化焼成という焼き方もあります。
こちらは焼成時の酸素を十分に供給して焼く方法なので、クリアに仕上がります。
よく言えばきれい目。わるく言えば釉薬の変化がない平面的な作風になります。
なので、酸化焼成の場合は、釉薬を掛け分けたり、こすったり、一手間掛けてから焼かないと、きれい過ぎて変化のない作品になってしまいます。
陶芸の入門者の場合は酸化焼成でもいいのですが、一度還元焼成の作品を経験すると、還元で焼かないと満足できない方が多くなります。
いわゆる古代から伝わる名品と言わているものは、登り窯や穴窯などで焼かれているので、必然的に還元焼成での作品になるんですね。
そのため名品には還元焼成で焼かれたものが多くなるんです。
もちろん現代の陶芸家によっては、電気窯で酸化焼成で焼いても立派な作品を作り出せます。
しかし、これは陶芸家レベルでの話。
初心者の方は釉薬をサラッと掛けて焼くだけの方が多いので、還元で焼いた方が、いい作品に仕上がります。
特に土の雰囲気を見てください。
酸化焼成と還元焼成の土の焼きの質感は全然違うものになります。
関東の埼玉とかで、陶芸体験で還元で焼くには
陶芸体験でも初回から渋めの作風に仕上げたいなら、還元焼成で焼ける所を探してください。
還元焼成で焼ける窯を持っている所は、ビルなどのテナントだと正直厳しいです。
還元で焼く窯は煙突を付けないといけないので、ビルなどでは防火上、オーナーの許可がおりないからです。
なので、地面に直接窯を置いて窯小屋で焼いている教室や陶芸所で陶芸体験すれば、還元焼成での作品が作れます。
このあたりの所は結構知らない人も多いので、こだわりの作品を作りたい方は、焼成方法にもこだわっている陶芸場所を選んだ方がいいでしょう。
関東で還元で焼ける所を選ぶなら、ずばり地方です。
あるいは都内とかなら、多摩とか田舎方面。
都心のど真ん中ではまず電気窯での酸化焼成となります。
生まれて初めて陶芸体験をするのなら、正直その違いはあまりわからないかも知れません。
なので、近場で済ますのも手です。
どう焼くかより、電動ロクロとかでの作陶の方が大事ですものね。
しかし、陶芸体験2回目以降とか、こだわった渋めの作風のものを作りたくなったら、焼成方法もチェックしてみてください。
その際は前回作ったものも保管しておきましょう。
陶芸体験で還元で焼いたやつとどう違うのかを知るのも陶芸の楽しみです。
土や釉薬の質感、全体的な雰囲気が全然違うものになると思いますよ。
(土と釉薬の種類にもよるのですが)
関東の埼玉とかで陶芸体験の電動ロクロを楽しくするにはのまとめ
陶芸体験と言っても、いろんな種類があるので、電動ロクロがやりたいのか、手びねりで作りたいのかをよく考えて決めましょう。
まるっきりわからなかったら、とりあえず何でもいいので、陶芸体験をやってみましょう。
で、2回目とか、もうちょい渋い作品が作りたくなったら、焼成方法にこだわって還元焼成とかで焼いてくれる陶芸体験の場所を探しましょう。
酸化焼成と還元焼成との作品の違いを見つけるのも陶芸の楽しみのひとつです。
ではみなさん、ぜひ陶芸体験などで作陶を楽しんでください。
面白いですよ。
****************
ツイッターもやってます。↓
Tweet
インスタグラムはこちら
https://www.instagram.com/touhatisan/
陶芸体験なら
陶芸教室 陶八さん
陶芸体験の詳しくはこちら。
会員さん希望の方はこちら。
陶芸会員さんも募集中
詳しくはこちらから。
※ YouTubeにて
陶芸教室 陶八さん by行雲 を絶賛放映中!
チャンネル登録もよろしくお願いします。